| 武将データ | ||
| なまえ | ほり ひでまさ | 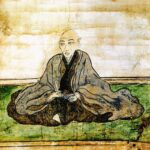
Wikipediaより |
| 出身 | 美濃国 | |
| 家紋 | 三盛亀甲に花菱 |
|
| 主家 | 織田家→豊臣家 | |
| 享年 | 37歳(1553~1590) | |
もくじ
堀秀政の名言
『新人はまず、受付にだせ』
解説は下記記載
堀秀政ってどんな戦国武将?
信長からの抜擢
秀政は父:秀重の子であり、信長から5千石与えられていた、そこそこの出自です。秀政は幼い頃から細やかな配慮、仕事ができるとの評判があり、13歳の時に信長に見いだされて小姓となりました。
16歳では足利義昭の仮住まいの普請奉行を担いました。若くして将軍と関わらせることに信長の信と政務に優れた秀政の腕が感じられます。この後も他の奉行職に就き、その手腕を振るったといわれています。
従兄:奥田直政との勝負
秀政は幼少期、一向宗の僧であった伯父に育てられており、その時、同じ時を過ごしたのが従兄の奥田直政です。
二人は伯父から、「これから、先に手柄を挙げた方にもう一方が従い、家を盛り立てるように。」と諭され、この勝負を受けます。結果的に秀政の方が先に功を挙げたため、奥田直政は『堀直正』と姓を改め、堀家に尽くすようになります。後々、直政は天下の三陪臣と呼ばれるくらいの存在になり、本当に堀家を支える存在となっております。
軍事面でも活躍
1575年、22歳の時には、政務だけでなく、戦場でも活躍を見せました。越前一向一揆の討伐から本陣側近として初参戦。その2年後の紀伊雑賀討伐では本陣から離れて一隊を指揮するまでになっており、出世のスピードからも、戦上手であったことが伺えます。
長久手の戦いでの唯一の戦果
本能寺の変によって信長が明智光秀に殺されると、羽柴秀吉の配下となります。秀政が一番活躍をしたのが、秀吉と徳川家康が争ったことで知られる小牧長久手の戦いの一つ、『長久手の戦い』です。
家康が小牧山城で守備を固め動かなかったので、両軍にらみ合いの膠着状態がつづきます。そこで、羽柴陣営の池田恒興が別動隊として三河を攻めることを秀吉に提案し、承認されます。ここに羽柴秀次と秀政が帯同します。
別動隊とはいえ、2万の軍勢で動いたため、家康陣営に察知されてしまいます。最後方にいた秀次が榊原康政の奇襲に遭い、為す術なく壊走します。秀政は秀次の隣に布陣していました。
後方から聞こえてくる銃声に嫌な予感を感じる秀政。斥候を出すと、徳川軍の急襲を知ります。すぐさま秀次を助けようと進行方向を反転させ行軍すると、秀次の重臣である田中吉政やってきて「徳川の襲撃を受けたため、すぐに備えを詰めよ」と言いに来ました。
本来、伝令は端役の兵がやるもので、重臣が単騎でやってくるなど有り得ません。詳しい状況を聞こうとしても「戦況が混乱していて詳しくは分からない」とされ、行ってしまいます。
このやりとりから、秀政は重臣の吉政が伝令をするぐらい部隊が壊滅していて、駆け付けても救援は難しいと判断。そこで秀政は、川が前方にある丘に移動し、敵を待ち構える布陣を取りました。
秀政は、敵が秀次に完勝した勢いのままに、こちらにも攻めてくるに違いないと予想したのです。この予想は的中します。敵が見えてくると、配下の兵に「この有利な場所から決して動かず、敵が近づいてから一斉射撃せよ」と伝えます。しかも騎馬兵一人に付き100石の褒章を出すことも伝え、モチベーションを挙げました。
一方的はというと、勝利の勢いそのままにこちらに向かってきます。隊列の整った秀政の布陣に、榊原康政はストップをかけますが、時すでに遅し。突撃してくる徳川兵を十分引き付け、かつ川で敵が足止めされたところを一斉射撃。高地で狙いやすかったこともあり、ばたばたと敵を討ち倒していきます。
結局、この秀政の機転が功を奏し、敵兵のおよそ10分の1の兵を倒すという大勝利を挙げました。この戦いでは池田恒興ら、秀吉側の将兵が討ち取られているため、全体としては敗戦という扱いですが、唯一の局所的勝利を収めたことで、秀政の武名を急上昇させることとなりました。
『名人久太郎』の異名
秀政の愛称は『名人久太郎』とされています。久太郎は秀政の本名、堀久太郎秀政からきてますが、『名人』とは何のことでしょう。
それは、『統治の名人』です。
とはいうものの、決して誰もが驚くような政治手腕を発揮していたわけではありません。
その逸話は、ある立札の設置に始まります。その立て札には、20~30か条に渡る、秀政の政治の至らなさを綴ったものでした。これを読んだ家臣は書いた者を探し出して処罰すべしと提案しますが、秀政はこの批判が綴られた札を読むと、手を洗い口をすすぎ身を清めた後に、持って手に掲げ、大事に扱う仕草をしました。
そして、「このような諫言をしてくれる者が他にいるだろうか。これは点が自分に与えてくださった家宝である。」といって、家の箱に大事に納めました。そして奉行を集め、批判された内容一つ一つについて改め、改善していったといいます。家臣だけではなく町人や百姓にもその姿勢が改められることとなり、知らぬものの諫言を素直に聞き入れる度量の深さから、『統治の名人』として称えられるようになったということです。
名言:新人はまず、受付に出せ
政秀は隊に志願してきた者を1ヶ月間受付のポジションに配置させました。秀政は、客の受付の対応はその者の本質がでると考え、それを見てから配属を決めました。
また、配属を決めるのは受付を勤める最終日でした。秀政は新人に「ここでの職務は務まりそうか?」
と聞き、もし務まりそうもないと答えたら、嫌な顔せず転職を認めました。そして最後に「もし次の職と比べてこちらの方が合っていたら遠慮せず戻って来い」
と言ったそうです。
秀政、良い上司ですね。信長からの信が厚かったのも頷けます。
最後に余談ですが、表中に載せた秀政の肖像画は自画像であるという説が濃厚です。絵も上手ですね。